
田村 浩二さん
1985年生まれ。料理人として13年間レストラン業界で働く。シェフとして働いた2年間で、世界のベストレストラン50の「Discovery seriesアジア部門」選出、「ゴ・エ・ミヨ ジャポン2018 期待の若手シェフ賞」受賞。香りをテーマに様々なプロダクトを開発。現在は「Mr. CHEESECAKE」の他、複数の事業を手掛ける事業家、経営者として多方面に活躍。
創業当初から変わらない名前と形。なぜ Mr. CHEESECAKEは長方形なのか?

田村さん、本日はよろしくお願いします!Mr. CHEESECAKEの商品に込められた思いと、それを伝える・届けるための裏側のお話をたくさん伺いたいです!

よろしくお願いします!
Mr. CHEESECAKEといえば、言わずもがな極上のチーズケーキを販売しているEコマースですよね。Eコマースで世に広める商品として、チーズケーキを選んだ理由は何だったのでしょう?

単純に「好きだから」というのが大きいです。
それともう一つ大きいのは、僕はフランス料理店でシェフをやっていたんですけど、その時お店に母が来てくれて、「美味しかったけど、よくわからなかった」と言って帰っていって(笑)
ミシュランを目指すような料理は鮨や和食以外は、どうしても新しいもの、奇をてらうようなものを目指しがちになってしまいます。それだと一部のFoodie(食べ物に関心の強い人)にはウケますが、複雑すぎて一般の方には「?」となってしまう。そういったことに常々疑問を抱いていたところに母の強烈な一言でした。自分としても「まぁそうだよね、でもなんかこれでいいのかな?」と感じたんですよね。
そこで今までの知識と技術で、もっと単純で美味しいものを作ってみたらどうなるんだろうと考えたのもきっかけです。
それでチーズケーキを作り始めて、販売を開始されたと。

販売を開始というか、最初はInstagramに投稿しただけでした。「究極のチーズケーキを作っています」って。そうしたら、投稿を見た人から「食べてみたい!」という声を頂いて、DMのやりとりで販売し始めました。






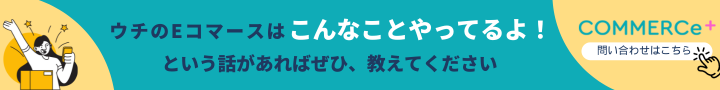
インタビュー、文:大西 真央
編集:阿部 圭司
写真:阿部 圭司


