
木村 祥一郎さん
木村石鹸工業株式会社の代表取締役。1995年大学時代の仲間数名と有限会社ジャパンサーチエンジン(現、株式会社イー・エージェンシー)を設立。以来18年間、商品開発やマーケティングなどを担当。2013年6月に株式会社イー・エージェンシーの取締役を退任し、家業である木村石鹸工業株式会社へ。2016年9月、4代目社長に就任。OEM中心の事業モデルからの自社ブランド事業への転換を進め、石鹸を現代的にデザインしたハウスケアブランドを展開。
老舗石鹸メーカーによる、自社ブランドの立ち上げと “買い戻す” OEM
木村さん、本日はよろしくお願いします!
木村石鹸といえば、お風呂まるごと洗浄剤や自動製氷機の洗浄剤などのちょっとニッチな専用洗剤「C SERIES(Cシリーズ)」や、石鹸職人のこだわりが詰まったハウスケア&ボディケアブランド「SOMALI(ソマリ)」をはじめ、様々な自社ブランドを展開されていますよね。まずはこれらの自社ブランド展開を始める前の木村石鹸について、ルーツをお聞かせください。

木村石鹸は、名前の通り石鹸にまつわる色々なものを作っているメーカーです。創業は1924年(大正13年)、伝統の「釜焚き」製法でこだわりの石鹸を作り続けています。

初期の木村石鹸は、生協向けのOEMが中心だったのですね。

はい。しかし、それも2006年頃から立ちいかなくなりました。
リーマンショックやデフレの影響で不況が続く中、原料費がどんなに上がっても、最終販売価格をメーカーの一存では上げられません。当然利益はどんどん減っていきます。それに加え、「増量して価格は据え置きで」等の要望にもなんとか対応していたものの、原料費の高騰は続き、現場はますます疲弊していきました。
2006年というと、木村さんはまだ木村石鹸に戻っていない頃ですよね。

そうですね。私が前職(株式会社イー・エージェンシー 取締役)を辞めて、家業である木村石鹸に戻ってきたのは2013年。この時点で営業利益は0になっていました。このままOEMだけを続けていてはジリ貧だと考え、自分たちで直接売ることを検討し始めたのがこの頃です。
販路を生協に頼っていたとはいえ、お客様の手元に届く最終商品は自社で完成させられていたので、商品開発には自信がありました。あとは自分たちの名前で売れる自社ブランドを作って、それをEコマースで売れれば、と。








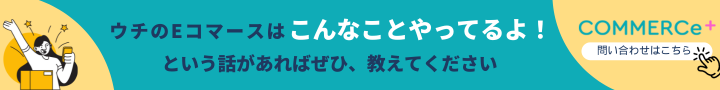
インタビュー、文:大西 真央
編集:阿部 圭司
写真:木村石鹸


